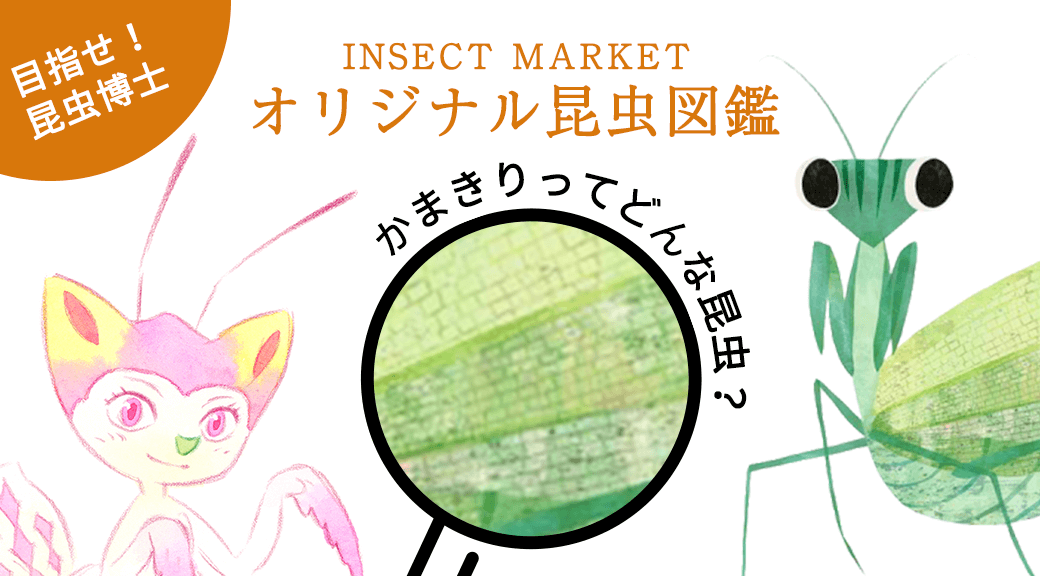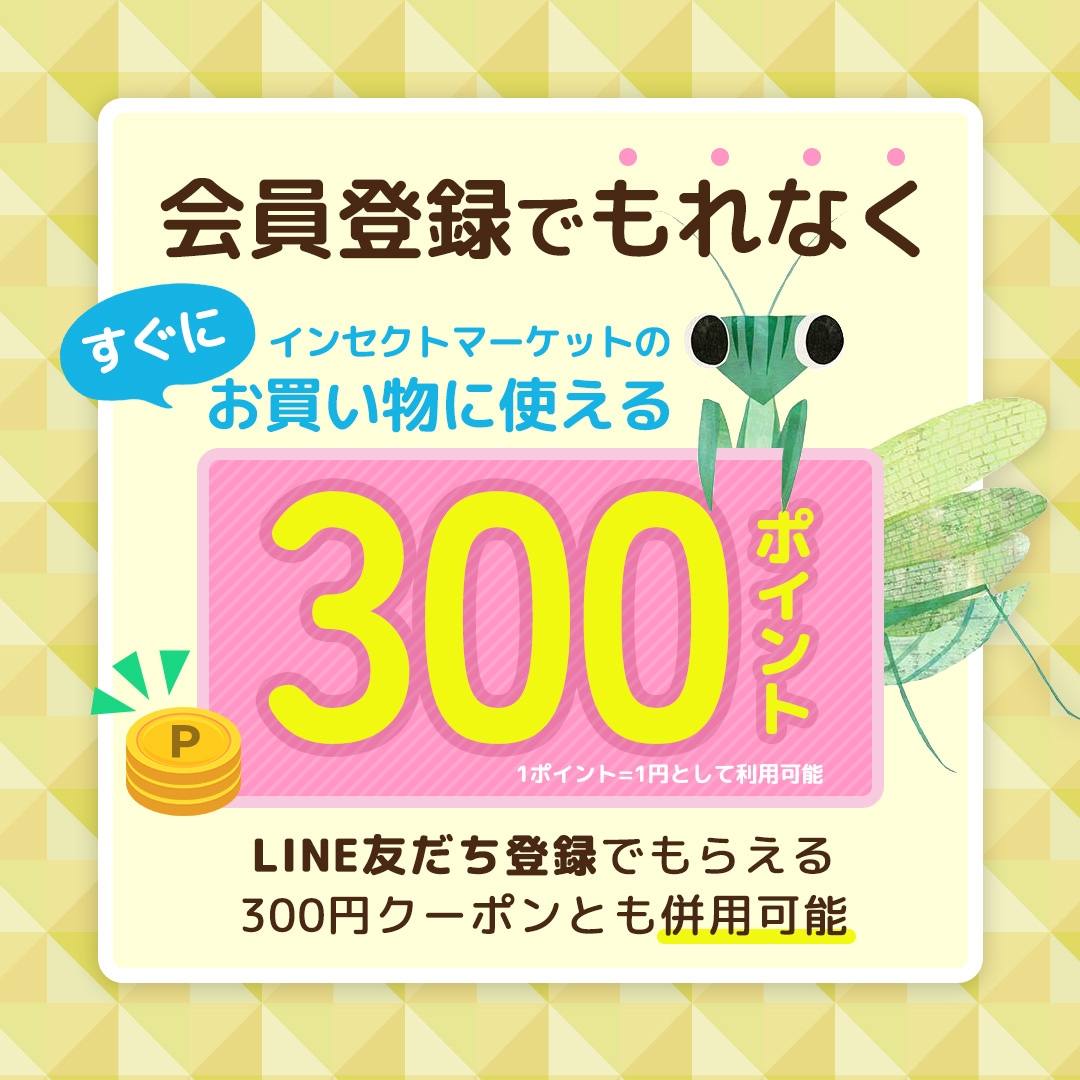専門家インタビュー:立教大学 スポーツウエルネス学部 准教授 奇二 正彦氏
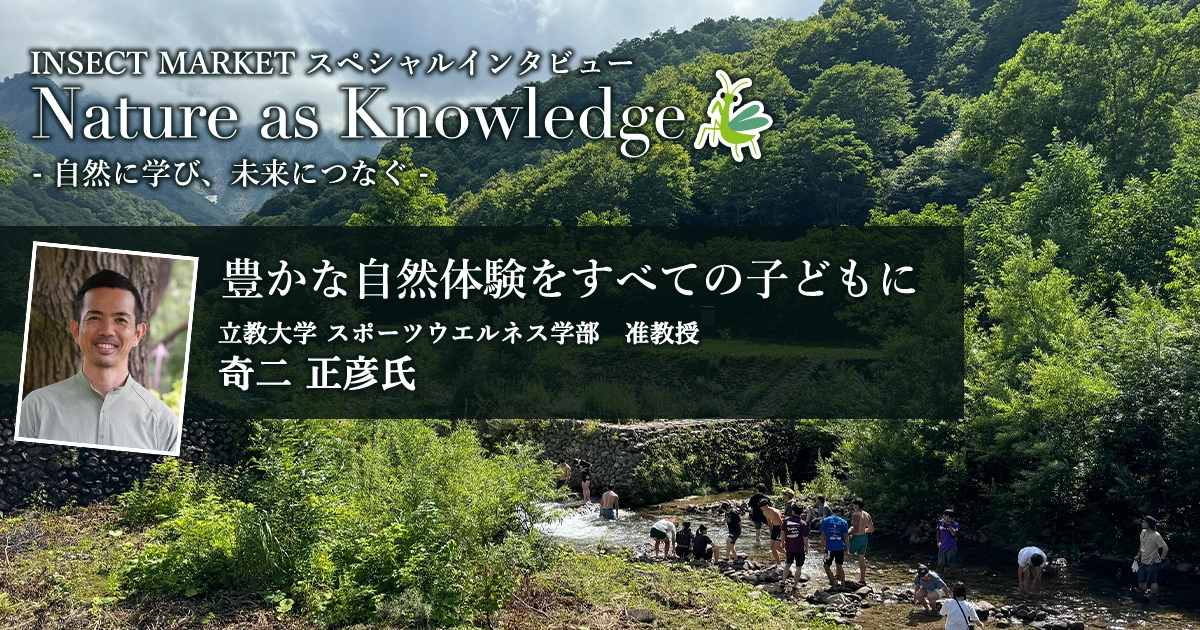
INSECT MARKETでは「遊びを学びに!自然体験」をテーマに、専門家と楽しむアウトドアイベントとして、5月に初のデイキャンプイベントを開催します。
記念すべき第1回は立教大学のスポーツウエルネス学部准教授、奇二正彦氏をお招きします。
環境教育・保全活動を軸とし、自然体験の心理的効果などを研究していらっしゃる奇二先生と、BBQ、自然観察、Beeハウス作りなどを楽しむ予定です。
奇二先生の今までの経歴や活動、子どもたちの教育についてをテーマにインタビューを行いました。
立教大学 スポーツウエルネス学部 准教授
奇二 正彦氏
専門は環境教育・保全活動。大卒後、NZのアートスクールで学び、自然学校レンジャー、動物写真家助手、環境コンサルの研究員、環境教育NPOスタッフとして活動。40歳で大学院に進学。
自然体験とスピリチュアリティとの関係について研究し博士(スポーツウエルネス学)取得。
現在、立教大学スポーツウエルネス学部准教授。スキー、キャンプなどの野外実習の他、生物多様性や社会の持続可能性についての講義やゼミを展開。

奇二先生の現在の研究について教えてください。
現在は、人が健康になる方法の一つとしての自然体験をテーマに研究しています。
具体的には、大自然、あるいは身近な自然環境での種々の体験が、ストレス軽減、畏敬の念、スピリチュアリティ、生きがい感等と関係するか、心理学的、生理学的な検討をしています。
また、そうした自然体験とはどのような自然体験なのかを検討し、アクティビティ開発を行っています。
大学でのゼミのコンセプトは2本柱で、
【1】自然体験と健康との関係
・授業で寺社林や、新座キャンパス等で1時間程度の自然観察を行い、直接的に心身の変化を体験する。
・心理学的検討(アンケートやインタビュー)、生理学的検討(唾液を採取してストレス物質の増減を分析)等の実験を行う。
・自然体験と健康との関係に関する論文を読む。
【2】社会の持続可能性
・環境問題の現状把握と、その解決のための国際的な取り組みなどを概観する。
・大規模畜産と温暖化の関係、ファッションと環境破壊の関係など、身近なことをテーマにした映画を見る。
・大手アウトドア企業のスタッフや、アーティスト、プロスポーツ関連のサステナブルに関するファシリテーターなど、多様なゲストスピーカーを呼んでディスカッションする
・生物調査、ビオトープ作りなどを体験する
といった感じです。
自然体験と人の心や健康がどのようにつながっているかといった研究は大変興味深いです。
環境保全が人類全体の課題であるこれからの時代には、自然の大切さを再認識し「自分ごと」にしていくという意味でも大変重要視される分野なのではないかなと思いました。

このような研究をされていることに、先生の幼少時代も少なからず影響しているのではないかと感じたのですが、どのように過ごしていらっしゃいましたか。
静岡県田方郡函南町で生まれ育ちました。
小学生の頃から、友達と川で泳いで魚を捕まえて焼いて食べたり、雑草を食べて下校したり、裏山で秘密基地を作ったり、釘を炭で熱してナイフを自作したりして遊んでいました。また、近所のクヌギ林の中に、陶芸家と画家の夫婦が家とアトリエを自ら建てて住んでおり、そこで陶芸や絵画を習ったり、木にぶら下げたブランコで遊んだり、五右衛門風呂に入ったりしました。
地域には弥生時代の横穴などの遺跡をはじめ、神社や寺も多かったです。
よく昆虫を採りにいっていた大仙山という標高160mほどの低山には、仏舎利塔や鐘撞堂があり、露出した岩の斜面には聖徳太子の生涯や薬師如来が刻まれ、その山の麓にはハスの花が美しい池があったため、幼い頃からなんとなく死後の世界や仏教を身近に感じてきました。
高校で地理学を教えていた父と、小学校で国語を教えていた母の影響で、小さい頃から本をたくさん与えられました。
また、夕食時はテレビを消して、対話をしながらご飯を食べるルールだった気がします。
家族で旅行もたくさん行きましたが高級ホテルなどに泊まった記憶はなく、いつも民宿や国民宿舎でした。
そのほかにも、父が文化的で活動的だったため、サイクリング、キャンプ、登山、海水浴、スキー、美術館巡り、クラシックコンサート鑑賞など、今思えば豊かな体験をたくさんさせていただいた気がします。
母も独特な人で、小学校の国語の教科書を、「すべて自分の言葉に訳しなさい」などという教育を受けました。
「自分の言葉に訳す」とは、大変面白い教育方法ですね!
もう少し詳しくお聞かせいただけますか。
具体的には、
・国語の教科書で扱われている小説やエッセイなどから、取り組む作品を決める。
・次に、その作品の題名と作者、最初の一文から「。」まで声に出して読む。
・読んだ文章に対して、そこで表現されていることを自分が他人に伝えるとしたら、こういう表現になるかな?という変換を脳内で行う。
・変換できたら、その内容を口頭で伝える。
・変換できなかったら、もう少し読み進めたりして、理解できたら口頭で伝える。
それに加えて母が、「なぜ登場人物はそのセリフを言ったり、その行動をしたと思う?」
といった問いかけをし、それに答えていた記憶があります。
自分の言葉に変えるということ、理解力や表現力が高まりそうです。
早速、我が家でも取り入れてみます!

環境教育・保全活動を専門としている奇二先生自身が考える「子どもたちへの教育についてのポイント」はありますか?
個人的には、小学校中学年くらいまでに、自然体験、野外活動、文化的な体験、哲学的な対話、旅行、宗教的な体験、地理的な遊び(例えば近所の川の源流を辿ってみるとか)、伝統文化に触れる、読書などはした方が良いのではと思います。
これからの教育の場にはどんなことが必要だと感じますか?
平時は、情緒教育や、AIや英語や運動や金融や非認知能力や表現力、VUCA耐性やSTEM的教育などが大事だと思っています。
一方で、生きていれば地震、戦争、噴火、テロなどの有事も発生します。
そうした際、生き延びる知恵や身体性を持っているべきなので、両面から教育を行うべきかと思います。
アウトドアで行う焚き火やキャンプ、自然観察の知識は、生き延びる知恵や身体づくりにも繋がりますね。
また、人に迷惑をかけなければ何をしても良い、という倫理観から、もう一つ上の倫理観や哲学を育むべきだと感じています。
日本は世界でもその意識がかなり高い国なので、これからも大切にすべき価値観だと思います。
具体的には、豊かな自然体験をして、その自然に感謝する態度(お天道様が見ていると言った感性や、巨木に手を合わせる感性など)を育んだり、ご先祖様が見ているから恥ずかしいことはすべきではないといった、宗教的なのに宗教ではない感性などがそれに当たるかと思います。
この感性が環境保全への意識を育むことになるのではないでしょうか。
確かに日本は食べ物への感謝の深さや、無機物や植物などを生き物のように扱うような意識が特徴的だと言われていますね。宗教的なのに宗教ではない感性が大切、と言われるととても納得します。

この記事を読んでいる方はお子さまがいらっしゃる親御さんが多いのですが、子どもたちと関わりの多い保護者や教育者に大事にして欲しいと思うものは何ですか?
親が本当に好きなことをしていたり、何か向上するために努力している姿を見せるべきだと思います。子どもはそれをみて、生涯その姿に影響を受けるからです。
あとは当たり前のことですが、親の願望やルサンチマンを子どもに押し付けず、幼少期はひたすら子供が目を輝かしたり、熱中するポイントを見つけることだと思います。
例えそれが、将来お金にならなそうだとしても、思い切りそこに熱中させるのが良いと思います。
熱中できるものはトライアンドエラー、発見や改善などのプロセスが濃密で主体的なので、その経験に価値があると思います。
それでは最後に、未来への展望をお聞かせいただけますか?
子どもたちのことを考えた際、理想は、幼少期から豊かな自然体験をすべての子どもがすべきです。
また、小学校以降は、全ての教科に環境教育を入れるべきだと思います。そうすれば、持続可能な社会に関する情報格差はなくなり、意識高い系などという言葉もなくなります。
また、目指したい社会は「自然として生きる」社会です。
現代人である私たちは、自然を客観的にみて、資源を収奪したり、その反対に楽しんだり保護したりしてきましたが、本来人間は、自然から直接恵みを得るからこそ、その自然を大事に扱ってきました。
現代はもっとエネルギーを自分で作り出す生活を取り入れる必要があるのではないでしょうか。
例えば、コスパが良くなっているソーラー発電と蓄電池を組み合わせて利用したり、農的コミュニティにサブスクして、月一農業をしつつ、現場の農家さんから安全な野菜や米を送っていただくといったことも可能です。
また、自分たちの出す生ゴミも、コンポストにして、循環を取り戻す。
そのように、エネルギーや食を数パーセントであっても自分で作り出す「サブシステム」を暮らしに取り入れていくことで、「自然と生きる」というような価値観が醸成されるのではと思っています。
奇二先生、たくさんのお話をありがとうございました!
奇二先生には、5月のINSECT MARKETデイキャンプイベントでも、講師としてご協力いただきます。
楽しく学びのあるイベントとなると思います。ぜひ皆様ご応募ください!
第一回デイキャンプ・イベント詳細

・内容:BBQ(火おこし体験・カレー作り)、生き物調査&講座、ミニBeeハウス作成
・レベル:キャンプ/アウトドア初心者向け
・場所:高尾の森ワクワクビレッジ(現地集合・解散)
・日時:2025年5月10日(土)10:00-15:00
・参加費:8,000円/1名(施設利用料/材料/道具レンタル費込)大人子供同料金
・対象年齢:5歳(年長)〜小学生向け
※本イベントは安全対策の観点から、5歳以上のお子さまを対象としております。誠に恐れ入りますが、乳幼児のご同伴はご遠慮いただきますようお願いいたします。
・付添:子ども2名に対して保護者1名、子ども3名の場合は保護者2名
・募集人数:8組程度(応募多数の場合は抽選となります)
・備考:INSECT MARKETのお洋服ご着用にてご参加いただける方
・応募締切:2025年4月7日(月)